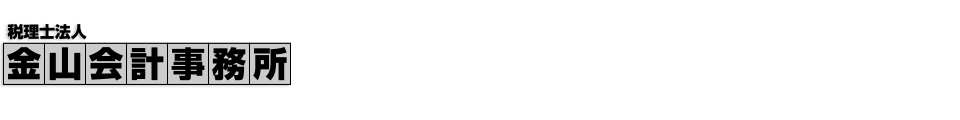税務コラム
税務コラム
税法違反被告事件の裁判を傍聴して No.15
本件事件に租税法学者及び顧問税理士として関わり、弁護団会議にもその日程の殆どに参加し、公判期日には法廷での傍聴を通じて、感じたことは、本刑事訴訟において先ず適用されるべきは、一般刑法ではなく、行政刑法としての租税刑法が適用されるべきであるということです。すなわち、一般刑法と租税刑法は、一般法と特別法との関係と類似したものと考えられ、本件事件は租税法という極めて政策性の高い特殊な行政法規に関わる事案であって、租税刑罰法規の解釈適用にあたっては、租税法に関する原則や法律の趣旨が考慮され、反映されるべきであるからです。前回までにも述べているように、わが国の法曹関係者には、教育課程の中での租税刑法を含む専門的な租税教育はなく、また、司法試験においても租税法は選択科目となっており、受験者は7%弱という現状にあります。
弁護団会議(両罰規定のため被告会社に2名、被告人に4名の弁護士、オブザーバーとして元大学法学部教授1名、元東京国税局幹部職員1名で構成)において、筆者が租税法学者の観点から述べたことが、理解されず、毎回のように「それは民事事件の考え方であって刑事事件は別の考え方をします」と言われ、終いには、先生の考え方は全く参考にならないとまで酷評されたこともありました。事ほど左様に、検察官においては一般刑法概念である、例えば「概括的故意」を持ち出し、被告人が当時の関与税理士に別の意味で希望を述べた内容の一言を脱税の「指示」をしたと認定する等、また、裁判官においても、会計処理はともかく税額が算出されていればよいのではないかとの趣旨の質問をする等、学者の目には驚きとしか言いようのないものでした。
ようやく弁護団会議での参加者が一致した考え方を共有するようになったのは、10回公判を過ぎる辺りだったように記憶しています。ともあれ、それらの努力が、最終的には本件事件の最終局面の検察官による論告・求刑に対しての弁護人の弁論に結実しています。その弁論の冒頭において、弁護人らは、裁判所に「審理にあたり考慮していただきたい点」として、「被告会社と関係法人の関係、各法人と職長、職人らの関係等を理解するためには、建設業界における独自の慣習や取引実態、職人らの考え方等を理解することが不可欠である。法律家には法律家の世界、裁判所には裁判所の世界の常識や感覚、慣習があるように、建設業界には建設業界の常識、感覚、慣習がある。しかし、そのような業界内の慣習は、外部の人間から見たときには、一見すると非合理的で理解し難い面があるのは、世の常である。然るに、本刑事訴訟は、被告人らに対し刑事処罰をもって臨むかどうかを判断していただく場である。裁判所の審理の結果は、被告人らにとって極めて重大な不利益を生じさせるものであり、法律家の常識に囚われず、慎重なご判断を願うものである。」としている。
本件刑事事件では、逋脱(脱税)額そのものは争ってはいません。しかし、本来、税法違反被告事件、すなわち脱税事件の起訴は、一般には逋脱所得、逋脱税額の多寡によって分かれるとされるところから、直接は関係しないとしながらも、起訴状には、「本件は○○○○円もの多額の脱税事件である。」との記載がなされるのが、一般的です。ということは、関係ないとは言いつつも、一応の量刑の判断要素となっているのが現状と言えます。
したがって、量刑の一応の判断要素ともなる脱税額の算出は、公正な判断の下、正確な計算が不可欠となります。然るに、法廷に顕出された、いわゆる脱税額は、あまりにも不正確なものに戸惑います。これについては、本件事件とは別に、行政面から所轄税務署による更正通知書及び加算税の賦課決定通知書に記載されている税額を争うことになり、その後の手続は通常の租税訴訟と同様の取消訴訟を、通常裁判所に提起することになると思われます。(つづく)
文責(G・K)