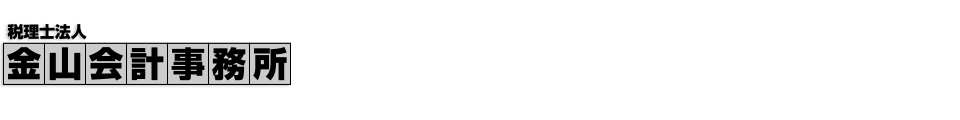税務コラム
税務コラム
税法違反被告事件判決への疑問 その4(正しかるべき司法も盲いることがある?)
前回までのコラムで、旧関与税理士が関与先へのアカウンタビリティを十分に果たさないばかりか、課税当局及び司法当局の質問顛末書や検面調書の作成に当たっては、本人はもとより事務所、職員挙げて事実と異なる証拠を提示したり、証言することによって、納税義務者(被告人)らに自らの責任の転嫁を図っていたのではないかとの考え方を述べてきました。そしてこの点について、課税当局はもとより告発を受けた司法当局も「予断」を持って、それに基づくストーリーを描いたのではないか、そのことを、「正しかるべき司法も盲いることがある?」と表現しました。と言うのも、いわゆる租税犯罪の解明には、租税法特有の法規の複雑な政策的、技術的要素や不明確性を伴うところから、租税犯の本質的な構成要件要素である納税義務者の存否や範囲についての正確な認識にも困難を伴います。また、具体的納税義務の内容の認識には、複雑な租税法や関連諸法規に加えて会計原則等の正確な理解を必要とします。これらについては法律及び会計に精通した専門家にとっても容易なことではない側面はあるものの、本判決は、まるでそれから逃避するかの如く真正面からの法律判断、解釈を避け、ないしは誤って極めて短絡的に「推認による事実認定」によって結論を導いているように思われるのです。
本判決は、逋脱について、「法人税等をほ脱することの概括的な認識があれば足りると解される。」とした上で、被告人らは、「平成X+1年3月期の決算において、旧関与税理士が示した計算に関し、当初算出された利益額を約2億円から1億円に減少させる経理処理を行う認識があったことは明らかであり、この限度では特段争われていない。」としています。そこで、先ず「概括的な認識」について述べたいと思いますが、ここでの「概括的な認識」とは、税につき、その内容についてどの程度の知識を持ち、どの程度の税額を軽減したいという認識があったと認められれば、それを逋脱に向けられたものとして認定されるのか、客観的な基準が明確に示されてはいません。と言うのも、一般国民の税に対する感覚や認識は相対的なものであり、租税負担についてはできるだけ低い方が、高負担より好ましいと考えているでしょうし、企業経営者等の、いわゆる合理的経済人が税負担の軽減等を動機、目的として行動するのは通常であり、それは判例(名古屋高判平成16・10・28)も認めるところでもあるからです。
加えて、「当初算出された利益額を約2億円から1億円に減少させる経理処理を行う認識」があり、それを旧関与税理士に「概括的に指示した」と認定されていますが、当該認定にも疑問があります。残念ながら、企業経営者を含む一般国民に税に対する「認識」というか、「感覚」を問えば、税額や節税(脱税)だとか、あるいはそれらを実行して欲しい等の「意識」、「考慮」、もちろんそれらの指示など関係なく、殆ど例外なく、咄嗟に「半額ぐらいだったらいいな」という「希望にも似た答え」が返ってきます。これを裁判官が「概括的に指示」と逋脱認定できるものでしょうか、甚だ疑問です。況して、本件事件においては、旧関与税理士が、法人税法等に違反する経理処理をしていながらそれに気付かず、「当初算出された利益額約2億円」ではなく、決算月に突然に顕現した利益約1億円をどうにか処理したいという意思があった背景があります。
また、似て非なる概念として、「概括的故意」という概念がありますが、これは刑法一般で論じられるものであり、租税刑法特有の概念である「概括認識説」とはその考え方を異にします。本件事件において、一概に概括認識説が適用できるかどうかは疑問、議論のあるところです。何故なら、税についての認識の内容や程度については、概括認識説と個別認識説との対立が見られるからです。租税刑法上で概括認識説の適用が検討、考慮される場合は、申告所得額を超える所得が存することの認識があれば足りるとされ、その具体的な額、その算定を基礎づける個々の勘定科目や益金、損金等の個別的な認識は不要とされています。個別認識説は、それらとは反対に、故意の要件としてはそれでは不十分であり、上に述べた項目についての個別的な認識を必要としています。
逋脱の判断に係るこれらの概念については、下級審は、およそその所得についての概括的な認識があれば足りるとする、概括認識説を採るものも見られますが、学説、下級審の判断ともに個別認識説、概括認識説を採用するものが見られ、この点についての上級審の判断は示されてはいません。本判決は、概括認識説を採ることの合理性、適正性等について「推認される」こと以外には、この点の説明はありません。概括的な認識から逋脱を「推認」し、租税刑法上の逋脱犯(特別刑法犯)と認定するには、より慎重であるべきです。それは租税法自体が、憲法が保障する財産権に対する侵害法規であること、単純な行政犯とは異なり、特別刑法犯は身体拘束を伴う場合もあり、また、ひとたびマスコミ等の報道によって名誉が棄損されると、もはや回復が不可能となる虞がある人権侵害の問題、また計り知れない莫大な経済的損失を被らせる問題とも絡み、特に厳格に扱う必要があると考えられるからです。
このコラムで繰り返し述べてきているように、「租税法の規定は租税に関する固有の領域において、民刑事の一般法に対して優先的に適用されるべきものとしてほぼ完結的な法体系をなしており」(東京地判昭和61・3・1)、租税刑法における制裁法規においては、これに先行するいわば第一次的規範としての租税実体法の指導理念(租税法律主義)に遵い適用されるべきものと思われます。(つづく)
文責(G・K)