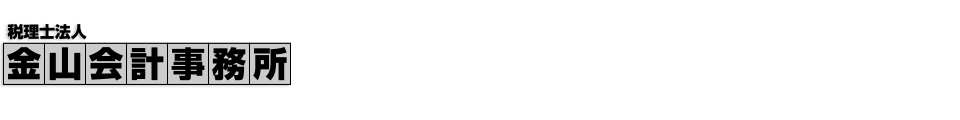税務コラム
税務コラム
租税不服申立について(審査請求「意見書」編…その3)
今回もこれまでに続き、原処分庁の答弁書及び意見書における主張及びその内容に対して請求人の反論として述べた意見について触れてみたいと思います。これまでこのコラムにおいて述べてきた内容、事柄との重複は可能な限り割愛するつもりでいますが、原処分庁は自らの発言に自信が持てないのか、何度も蒸し返しの主張、反論をしていますので、それらのうち、重要と思われるものについては、請求人として不本意ではありますが、重複して反論しています。原処分庁は、本件法人税等の更正処分等における実質的な費用収益等の帰属主体について、「本件各関係法人は法人としての事業の実体を有していないと認められる」と主張していました。そこで請求人は、反論書において、原処分庁の判断は誤りであり、法人税法第22条各項により当該取引を否定される理由はなく、仮に認められるとしても、当該処分の根拠となる法令が記載されていないと反論しました。
これに対し、原処分庁は「法人税法第11条の規定を費用収益の帰属認定の根拠とし、本件関係法人には、事業実体がないものと認められることから、請求人の各事業年度における所得金額を法人税法第22条等の規定に基づき、計算を行ったものであり、原処分に係る通知書に、根拠となる法令等は記載されているから、理由附記不備には該当しない」と密かにその反論書に「等」の一文字を忍ばせ挿入し、これに法人税法第11条の規定の役割を担わせている旨を強弁しました。そこで請求人は、法人税法11条が規定する実質所得者課税の原則は、本件更正処分等の事案には適用できず、近時の裁判例においてもこの原則を採用していない旨反論するや、一転、原処分庁の意見書においては、その主張をさらに変更し、根拠条文について「本件答弁書においては、法人税法第11条及び消費税法第13条の観点について検討しているものの、これらの規定に基づき判断したのではなく、あくまでも原処分庁が認定した事実を総合的に勘案した上で、法人税法第22条第2項に基づき、請求人に帰属する益金の額を判断しているものであって、誤った法令の適用の事実はない」と再度、その主張を変遷させている意見書を提出してきました。
すなわち、原処分庁は、当初、本件更正処分等の根拠条文は、法人税法第22条第2項だとしていたものを、請求人がこれに反論するや、法人税法第22条等だとし、「等」の一字を加えることによって、法人税法第11条を適用して計算を行ったとし、その主張を翻し、そして、更にその主張を変遷させたのでした。原処分庁の主張は、このように、根拠に乏しく常に恣意的、場当たり的であり、重要な局面において主張の変遷がみられ、極めて信頼性を欠く反論、主張(詭弁)という他はないものでした。因みに、法人税法22条各項は法人の各事業年度の所得計算の通則規定であって、決して否認規定ではありません。仮にこの規定に否認規定の役割を与えるとしても、前提として、この規定に使用されている用語の解釈及びこの規定の適用範囲等が明らかにされていなければなりません。
つまり、法人税法22条2項の解釈を通じた本件更正処分等に適合する税法規範を定立する(明示する)ことが大前提となります。何故なら、税法の条文だけでは、その意味内容を確定することができないからです。ところが、原処分庁の主張は、上に述べるように、コロコロと重要な局面において変遷がみられ、曖昧で、法人税法22条2項の意味内容が明らかではありません。それどころか、この点について、原処分庁は「法人税法22条2項の法律論的解釈について、意見を述べる立場にない」と、請求人の質問に正面から答えようとせず、憲法に根拠を置く租税法律主義を無視し、課税庁としての責任をも回避する回答をするばかりです。これでは、照らして判断すべき大前提としての法規範が存在していないことになります。その上、その大前提に当て嵌めて判断するべき、小前提としての事実認定についても、認定された筈の「事実」が虚偽であったり、捏造されていたり、違法に収集されたものであったり、強引に誘導された申述に基づくものであったりと、全く真実性、信用性、任意性に乏しいものであり、結果として、存在していないのです。
再三このコラムで述べているように、本件更正処分等が、「はじめに結論ありき」で、それに平仄を合わせようとする結果、あちこちに矛盾が生じ、原処分庁の意見書においては、恣意的、一方的な主張が目立ち、直接証拠を示すことなく、「いずれも理由がない」、「総合的に勘案した」などとしており、それらの主張の中身は、いわゆる「為にする議論」であって、杜撰性や曖昧性からくる論理破綻が随所にみられるところです。例えば、原処分庁の意見書において、要旨「関係法人には事業の実体がない」、「総合勘案すると請求人に帰属する」との主張を繰り返し行っていますが、収益の帰属判定において「総合勘案」では立証が不十分であることは明白です。また、原処分庁は、一貫して、本件各関係法人は法人としての事業実体がなく、請求人と同一と認められるとの主張をしていますが、本件各関係法人が建設業許可を取得していないと主張することは、その前提として、本件各関係法人が別法人であり、実体があることを認めていることを意味しています。しかし、原処分庁は、請求人と本件各関係法人とは別法人であることを認める一方で、本件法人税等の更正処分等においては、請求人と本件各関係法人とは一体であると主張しており、原処分庁の主張には明らかな背理があることになります。
加えて、建設業法との関連の指摘については、当該業法を所管する主務官庁は国土交通省であり、財務省所管の本件法人税等の更正処分等とは、一義的な関連性を有するものではないことはもとより、法令にはそれぞれの立法目的なり立法趣旨が存在します。財務省が所管する税法においては、課税の公平の目的から純資産増加説に基づき、最高裁は、「税法の見地においては、課税の原因となった行為が、厳密な法令の解釈適用の見地から、客観的評価において不適法、無効とされるかどうかは問題でない」と判示し、違法収益についても課税対象とする判断を示しています(最判昭和38 年10 月29 日訟月9 巻12 号1373 頁参照。)。本件の場合、仮に建設業法に違反していたとすれば、請求人の法人所得が課税の対象外となるかといえば、決してそうではありません。原処分庁が、主務官庁の相違する国土交通省に係る下請先の建設業許可取得の存否を取り上げ、敢えて議論を拡散、論点をすり替え、請求人を法令に違反する納税義務者であるかの印象操作をしているとしか評価できません。
原処分庁の意見書に使用されている「本件架空給与」という用語について、請求人は当該用語が原処分庁によって使用されることを認めているわけではありません。これにつき、原処分庁は、答弁書の中で「給与手当勘定」から本件更正通知書別表の「総勘定元帳に計上している金額」を減算した金額との差額としていますが、請求人においては、その差額についても認めていません。原処分庁が指摘する「本件架空給与」の実態は、元請の現場担当責任者に請われて同現場担当者らに一時的に貸し出した金員であり、それらは営業活動の潤滑油としての販促費、交際費の性格を有する販促費です。その経理処理に当たり、旧関与税理士に指示され、経理担当者が使用した科目名が適切ではなかったこと、また、そのことを旧関与税理士のI氏が原処分庁に理解可能な表現で説明できなかったところに本質的な問題があったと考えられます。しかも、本件差額分については、所轄税務署の過去の税務調査において、不適切との指摘を受け、その指導を受け容れて現金を戻し入れする等の処理済みであったもので、本件に関し原処分庁が、これを隠蔽、仮装を伴う「架空給与」と認定することは全くの事実誤認です。(つづく)