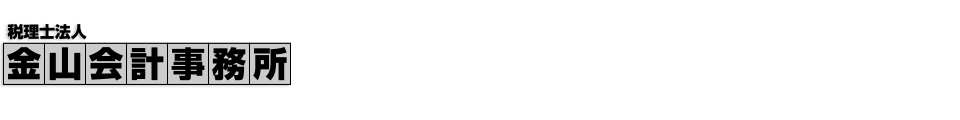税務コラム
税務コラム
国税不服審判所の役割とその存在意義 その30
本裁決は前回に見てきたように、その結論に至る立論自体に矛盾や誤りがあり、根源的な部分に疑問が生じるところから、常識的には、一般の納税者が札幌国税不服審判所の示した結論(裁決)に賛同、納得する者は多くはないと思われます。その最大の疑問として、租税行政庁は嘘を言っても構わず、納税者(国民)は嘘を言ってはならないとし、しかも、税務調査官の嘘を信じるか信じないかは、「納税者の自己責任」であるとし、その嘘につき、「税務署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示」と信じた納税者(国民)の方に落ち度があるとしていることです。また、審判所は信義則違反についての請求人からの指摘は、審判所が挙げているものに止まるかのように、租税行政庁にとっての不都合な事実を作為的に矮小化して記載していますが、これ以外にもこの税務コラムその26で触れているように、重大な信義則違反の事実が存在しています。
また、前回も請求人が触れているように、札幌国税不服審判所は、「本件各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額を計算すると、平成25年3月期及び平成26年3月期の法人税の所得金額及び納付すべき税額は原処分の額といずれも同額となることから、各更正処分のその他の部分については、不相当とする理由は認められず、平成25年3月期及び平成26年3月期の法人税の各更正処分はいずれも適法である」と結論付けています。そして、平成27年3月期については、原処分庁の給与手当の過大計上額の僅かな誤りを指摘する他は、「平成27年3月期の法人税の更正処分のその他の部分については、これを不相当とする理由は認められない」としています。しかし、これらは、札幌国税不服審判所が独自に調査及び計算をした上で、それぞれの期の法人税の各更正処分はいずれも適法であるとの結論を導いたとは到底考えられません。仮に、上記審判所が独自に調査及び計算をした上で法人税の所得金額及び納付すべき税額が原処分の額と同額と言うのであれば、原処分庁も審判所も機能せず、ダブルで法解釈を誤り、計算を誤ったことになります。
と言うのも、審判所は、平成25年3月期及び平成26年3月期並びに平成27年3月期のうちの一部の計算誤りを除く法人税の各更正処分のその他の部分については、「提出された証拠資料等によっても、不相当とする理由は認められないから、それぞれの期の法人税の各更正処分はいずれも適法である」との裁決をしています。ところが、請求人が審判所に提出した証拠資料等は、いずれも原処分庁の嘘や誤りを示す直接証拠ないし間接証拠等の重要書類であり、本件更正処分等自体を不相当と判断するに十分な説得力を有する内容であった筈ですが、審判所は調査や計算、検討をすることもなく原処分庁の本件更正処分等をそのままトレースしたと考えられるからです。
現に、当税務コラムのその20から22にかけて述べているように、「本件各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額を計算」にはその内容や計算に誤りが多く、また、それらは、請求人に対する当初更正処分及び現更正処分等に由来するものであり、したがって、本来その誤りについては、原処分庁か審判所かのどちらかの租税行政庁が正すべきものです。しかしながら、あれこれ理由にならない理由付けをして、職権での減額更正をどちらも行わないことから、令和3年5月から令和4年1月にかけて、請求人が更正の請求をしているのです。そして、その結果は、一部については更正処分の誤りを認め、更正の請求を認容して、国税の本税部分のみでも約1,700万円を還付し、その他については、更正をすべき理由がないとしており、請求人は、現在、審判所に「更正の請求に対しその更正をすべき理由がない旨の通知」を取り消して貰うべく審査請求をしています。
また、加えて請求人は審査請求の期間中に、数多くの反論書、意見書、口頭意見陳述における質問及び税理士意見書等の書面にそれぞれ証拠資料等を添付して審判所に提出していましたが、審査請求が終盤を迎えた時期に、KT審判官は、それらについて、「目を通していない」、「提出された資料等に係る原処分庁等への通則法97条に基づく質問、検査等の調査は行わない」ことなどを、請求人(代理人)に明言しました。このことからも、審判所の計算したものと「原処分の額とがいずれも同額」との記載が、どれだけ杜撰で説得力ないし合理性がなく、信用できないものかが想定できます。因みに、平成25年3月期、平成26年3月期、平成27年3月(及び平成28年3月期)のいずれの期にも事実の誤認及びそれに基づく計算誤りがあり、既に述べているとおり、それぞれの事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額について更正の請求をしているところです。
このように、原処分庁も審判所もダブルで認定や計算等を誤るなど、租税行政庁の計算は全く当てにならず、信頼の置けないものであるにも拘らず、審判所は叙上の裁決をしているのです。裁決書は、「本件調査に係る調査手続に違法はないとともに、本件各更正処分の理由附記に不備はなく、本件当初各更正処分を取り消し、処分理由を差し替えて本件各更正処分をしたことについての違法は認められず本件各更正処分等は信義則に反する違法な処分であるとは認められない」、「請求人は、実体のない架空の本件各外注費を総勘定元帳に計上し、法人税の課税標準を過少にした内容虚偽の本件各事業年度の確定申告書を提出しており、これは通則法第70条第4項第1号に規定する偽りその他不正の行為によりその一部の税額を免れていたものと認められる」、「本件各関係法人がそれぞれ申告した収益、費用等に係る業務及び取引は、請求人が行ったものと認められる」と判断しているのです。
しかし、審判所が裁決書で触れている「原処分の額といずれも同額」となるから法人税の各更正処分はいずれも適法であるとする裁決は、論理の飛躍であり、上にも述べたように、合理性が全くありません。原処分に数多くの違法や誤りがあり、そして納税者から更正の請求が出され、それを、一部であったとしても認容しなければならない内容や状態の更正処分に租税行政部内の番人としての審判所の判断に適法性、正当性があると言えるのでしょうか?「当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない」とする結論は、結局、いずれも立論を誤っていたり、請求人が求める通則法97条の「審理のための質問、検査等」を行っていなかったとの帰結になります。このような情況下にあってすらも、仮令、それが誤ったものであるとしても、審判所が公的な第三者機関としての機能を果たす努力をせず、唯々、原処分庁の主張を追認し、これにお墨付きを与える役割を果たすのみの機関となっているところが残念に思われるところです。
審判所の以下の認定についても、請求人が一貫して述べているとおり、そのように実体のない架空の各外注費を総勘定元帳に計上し、法人税の課税標準を過少にした内容虚偽の本件各事業年度の確定申告書を提出し、敢えて、偽りその他不正の行為によりその一部の税額を免れたことはありません。仮に、偽りその他不正の行為、いわゆる「脱税行為」と評価されるのであれば、典型的には、強制調査の過程でタマリ(隠していた現金や高価な物品などの現物)が発見される又は自白があるのが一般的です。しかし、本件の場合、タマリの発見も自白もなく、只々、原処分庁側の一方的な主張とそれを無理に立証すべく状況証拠が示されているのみです。審判所が、請求人は「実体のない架空の各外注費を総勘定元帳に計上し、法人税の課税標準を過少にした」と強弁するのは、原処分庁及び審判所が租税行政庁としての面子の維持、及び課税の論理から形振り構わず行っているものに他ならず、そこに法令の遵守、とりわけ租税法律主義の重視、納税者基本権擁護等の視点は脱落し、租税行政庁としての自覚、矜持が甚だしく欠落しているように思われるところです。
何故なら、原処分庁等の租税行政庁が請求人の法人税法等及び消費税法等の更正処分等を行うに際して、そもそも合理的な疑いを容れる余地がない程度の十分な証拠(直接証拠)がない中で、強引に「はじめに結論ありき」の方針で検察庁に租税法違反事件(脱税事件)として告発したことから刑事裁判が先行し、その判断(判決)が示されました。その公訴事実の本を辿れば、札幌国税局調査査察部査察第3部門の事実の認定を誤った告発にあり、そのことから、原処分庁及び審判所を含む租税行政庁は、当該判断(判決)を維持し、当該判決内容との平仄を図ることが至上命題となり、その姿勢が、後行する本件審査請求事件の審理に先立つ事実認定に当たって顕現化し、数多くの齟齬ないしは矛盾を生み、それを覆うべく「攻撃は最大の防御なり」とばかりに国家権力を濫用し、更なる虚偽事実の強引な主張、虚偽記載を続けているように思われるからです。
そもそもの本件各更正処分等の発端は、請求人の当時の関与税理士であったI税理士の事実誤認から、「期ズレ」は許されるもの、納税については、「今期払おうが来期払おうが、納めることには変わりなく同じことで、脱税するわけではない」との認識の下、変則的期中現金主義による会計処理、納税申告業務が行われていたことに基因しています。そして、当該確定申告書は、I税理士の事務所の職員によって作成され、署名押印については当時の法令により義務付けられているにも拘らず、I税理士の事務所の職員によって署名され、押印については、当該職員が請求人の本社事務室の引出しから許可を得たとは言え自らの手で取出して行っていたものであり、そこに請求人(及び当時の税務代理人としてのI税理士)の悪意はなく、当然ながら故意性は全く認められません。(つづく)
文責(G.K)